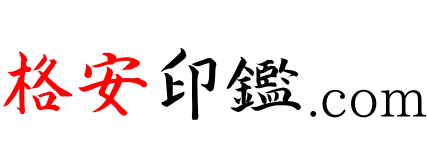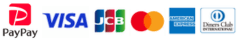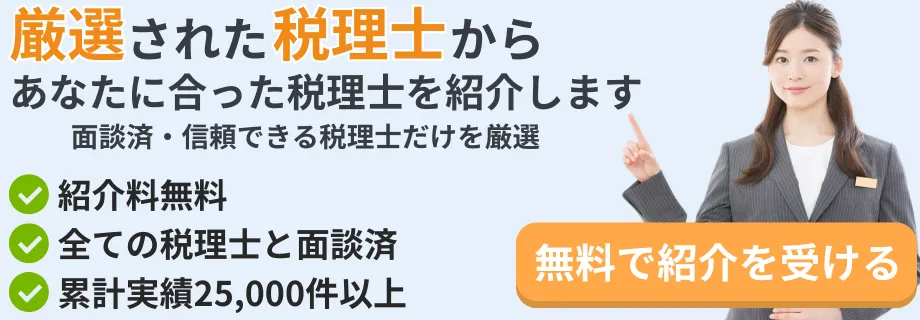この記事でわかること
この記事では、**「売上がどのくらいになったら顧問税理士を契約すべきか」**という疑問に答えます。個人事業主と法人それぞれの目安や、売上以外で契約を検討すべきタイミング、さらに顧問税理士をつけるメリット・費用相場についても解説します。
- 顧問税理士を契約する売上規模の目安
- 個人事業主・法人での違い
- 売上以外の判断ポイント
- 顧問税理士の費用相場とメリット
- よくある質問と注意点
顧問税理士が必要になる売上目安
個人事業主の場合
個人事業主は売上規模によって税務処理の難易度が大きく変わります。特に次の売上水準がひとつの目安です。
| 売上規模 | 顧問税理士の必要性 | 理由 |
|---|---|---|
| ~500万円 | 低い | 会計ソフトで十分対応可能 |
| 500万~1,000万円 | 検討段階 | 経理業務の負担増、青色申告控除の活用 |
| 1,000万円超 | 高い | 消費税課税事業者になる可能性、税務処理が複雑化 |
特に 売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるケースが多く、申告が一気に複雑になります。この段階で顧問税理士を検討する人が増えます。
法人の場合
法人は、売上規模に関わらず「設立直後」から税理士を契約するケースが多いです。
| 売上規模 | 顧問税理士の必要性 | 理由 |
|---|---|---|
| 設立直後~1,000万円未満 | 高い | 法人税・消費税・住民税など申告が複雑 |
| 1,000万~3,000万円 | 必須級 | 経理・資金繰りの管理が重要に |
| 3,000万円以上 | 必須 | 税務調査リスクや銀行融資対応 |
法人は個人事業主よりも税務の種類が多く、決算書の作成も専門的な知識が必要です。そのため、売上が小規模でも顧問税理士をつけるのが一般的です。
売上以外で顧問税理士を検討すべきタイミング
売上だけでなく、次のような状況も顧問税理士を契約する判断基準になります。
- 取引件数が増えたとき
領収書や請求書の管理が煩雑になる。 - 人を雇い始めたとき
給与計算や源泉徴収の処理が必要。 - 融資や資金調達を検討しているとき
金融機関への提出資料を税理士がサポート。 - 節税対策を考えたいとき
青色申告特別控除、役員報酬の設定、設備投資のタイミングなど、専門的なアドバイスが有効。
顧問税理士の契約費用相場
顧問税理士の料金は「月額顧問料」と「決算料」で構成されます。
| 売上規模 | 月額顧問料の目安 | 決算料の目安 |
|---|---|---|
| 個人事業主(~1,000万円) | 1万~2万円 | 8万~12万円 |
| 個人事業主(1,000万~3,000万円) | 2万~3万円 | 12万~20万円 |
| 法人(~1,000万円) | 2万~3万円 | 10万~15万円 |
| 法人(1,000万~3,000万円) | 3万~5万円 | 15万~25万円 |
※地域やサービス範囲によって大きく変動します。
顧問税理士を契約するメリット
- 税務処理の負担軽減
本業に集中できる。 - 節税効果
法人設立や経費計上のアドバイスが受けられる。 - 資金繰り改善
融資・補助金申請のサポート。 - 税務調査の対応
税務署からの問い合わせに心強い味方。
顧問税理士を契約する際の注意点
- 料金体系(定額か従量課金か)を確認する
- 業務範囲(記帳代行、給与計算、経営相談など)が含まれるかどうか
- 税理士本人との相性も重要
よくある質問
Q1. 売上が1,000万円未満でも顧問税理士は必要ですか?
A. 絶対に必要ではありません。ただし、経理が苦手・取引件数が多い・将来的に法人化を考えている場合は早めに契約すると安心です。
Q2. クラウド会計ソフトだけで十分では?
A. シンプルな事業なら可能です。ただし、節税や融資のアドバイスまではソフトでは対応できません。
Q3. 決算時だけスポットで依頼できますか?
A. 可能ですが、年間の経理状況を把握していない税理士だと割高になることがあります。継続的な顧問契約のほうが結果的にコストパフォーマンスが良いケースも多いです。
まとめ
- 個人事業主は売上1,000万円前後で顧問税理士の必要性が高まる
- 法人は設立直後から顧問税理士を契約するのが一般的
- 売上以外でも、取引件数の増加・人を雇うタイミング・融資を受けたいときは契約を検討すべき
- 費用は月額1万~5万円+決算料が相場
顧問税理士は単なる「経理代行」ではなく、経営のパートナーです。売上規模や今後の事業計画に応じて、最適なタイミングで契約を検討しましょう。